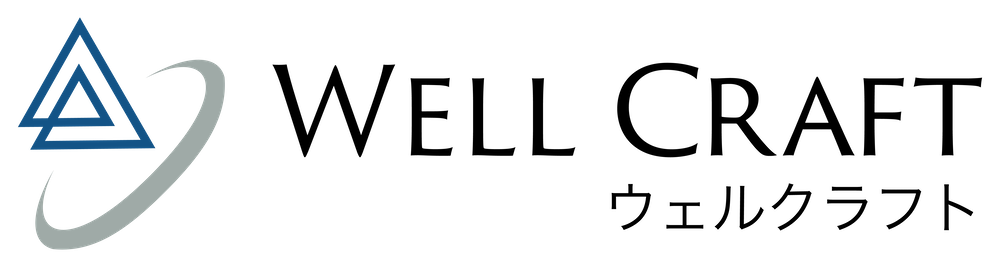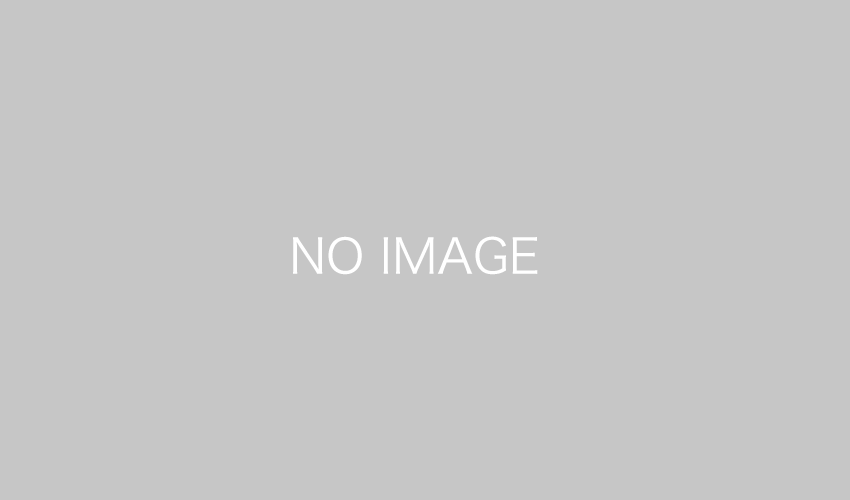デスクワークによる首肩こりと猫背の原因と改善法

デスクワークによる首肩こりと猫背の原因と改善法
長時間のデスクワーク。気づけば頭が前に出て、首や肩が重だるい――。一時的なほぐしで楽になっても、数日で戻ってしまう。その背景には、筋肉の緊張だけでなく、姿勢と呼吸の乱れが関わっています。本記事では、仕組みをやさしく解説し、今日から実践できる整え方をご紹介します。
デスクワークによる首肩こりと猫背の原因
前に出た頭が引き起こす筋肉の緊張
画面に集中すると、頭部が前方へ移動しがちです。頭はボウリング玉ほどの重さがあり、それを支える首・肩の筋肉は常に緊張状態に置かれます。緊張が続くと局所の血流が悪化し、酸素や栄養が届きにくくなることでこりや痛みにつながります。
呼吸の浅さが姿勢の崩れを助長する
頭が前に出る姿勢では背骨の上部(上部胸椎)が丸まり、胸郭が閉じて呼吸が浅くなります。すると首肩・胸郭まわりの呼吸補助筋が過剰に働き、さらに緊張が強まる――「姿勢の崩れ → 呼吸の乱れ → 筋緊張」の悪循環が生まれます。
首肩こりを悪化させる「上位交叉症候群」とは
アンバランスな筋肉が起こす負の循環
上位交叉症候群は、胸・首の前側の筋が短縮し、背中の深層筋(頸部屈筋群や肩甲骨周囲)が弱化することで、頭部前方位と猫背をつくるパターンです。この筋バランスの乱れを整えないまま表層だけをほぐしても、症状は戻りやすくなります。
一時的なほぐしで戻りやすい理由
緊張部位をほぐすと血流は改善しますが、姿勢を支える弱化筋がそのままだと、日常の座り方・視線・作業環境が再び同じストレスを生みます。「ゆるめる+支える」の両輪が必要です。
根本改善のための3つのアプローチ
① 施術で緊張をゆるめる
過緊張の筋や胸郭のこわばりを丁寧に解放し、血流と呼吸のしやすさを取り戻します。痛みや防御反応が強い部位には、反射を利用したやさしい手法を選択します。
② 弱化した筋肉を鍛え、姿勢を支える
深層頸屈筋、下部僧帽筋、前鋸筋などの姿勢保持筋の活性化が鍵。例として、顎を軽く引いて後頭部を長く保つ「チンタック+呼吸」、肩甲骨を下方・内方へ導くエクササイズ、胸椎を伸ばすスフィンクス姿勢など。回数は無理なく継続できる範囲からはじめ、痛みがあれば中止します。
③ 作業環境と習慣を整える
再発予防には、椅子の高さ・モニター位置・視線角度の見直しが不可欠。加えて、1〜2分のマイクロブレイクや眼精疲労のケアを「ひんぱんに少しずつ」取り入れます。
| 項目 | 目安 |
|---|---|
| 椅子の高さ | 座面で膝・股関節が約90°/足裏が床にフラット |
| モニター上端の高さ | 目線と同じ〜やや下(−5〜10°) |
| 画面距離 | およそ腕一本分(50〜70cm) |
| キーボード位置 | 肘90°前後/肩がすくまない高さ |
| 休憩頻度 | 30〜45分ごとに1〜2分のマイクロブレイク |
- マイクロブレイク例:ゆっくり3呼吸×2セット/胸を開くストレッチ30秒/遠く→近くを見る眼球運動30秒
整えて終わりではなく、「整え続ける」へ
身体は一度で完成しません。仕組みを理解し、日常で再現し、習慣として定着させることで、効果は積み上がります。ウェルクラフトは、施術の場で「なぜ不調が起きたのか」「どうすれば再び整うのか」という理由までお伝えし、ホームケアを含む生活デザインを伴走します。
理解 → 再現 → 定着。小さな一歩を重ねるほど、戻りにくい体に近づきます。
目次
※本記事は一般的な情報提供です。痛みやしびれが強い場合は無理をせず、医療機関や専門家へご相談ください。