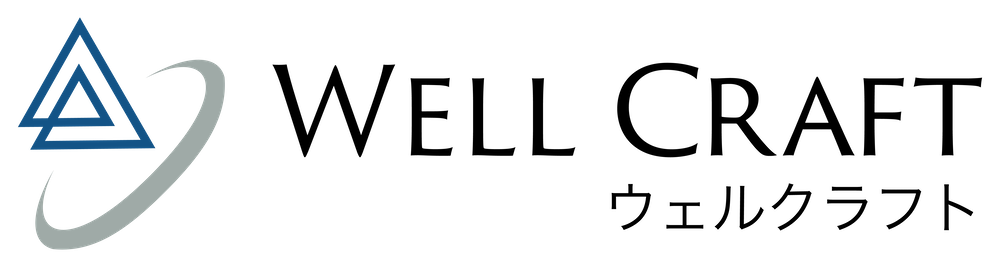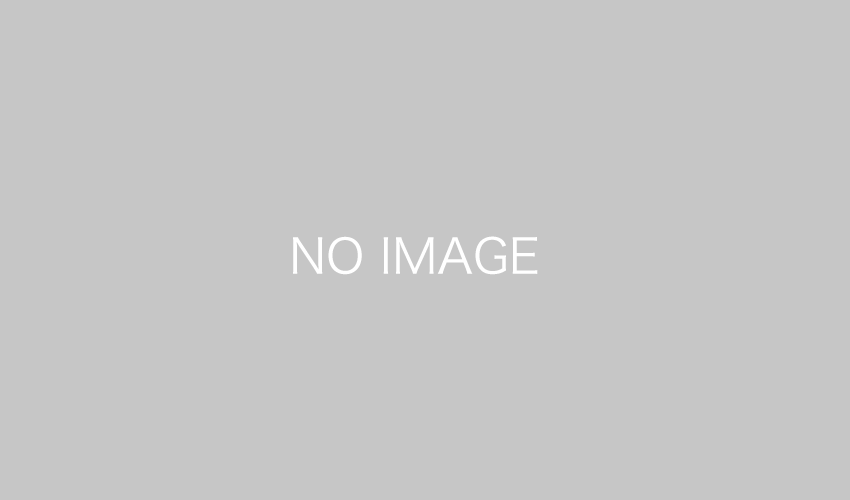反り腰と猫背の関係性

反り腰と猫背姿勢の関係性|バランスを取り戻すための整え方
「姿勢を良くしよう」と意識して胸を張ると、腰が反って疲れてしまう。
一方で、長時間のデスクワークでは背中が丸まり猫背になってしまう。
このように「反り腰」と「猫背」は一見逆のようで、実は深く関係しています。
本記事では、両者の関係を身体の構造から紐解き、日常でできる整え方をお伝えします。
なぜ反り腰と猫背は同時に起こるのか
上半身と下半身の“バランスの崩れ”
反り腰と猫背は、身体の上部と下部のバランスが崩れることで同時に起こります。
腰が前に反ると骨盤が前傾し、背骨のカーブが強くなります。その結果、胸椎(背中の部分)が丸まり、頭が前に出る姿勢が自然とつくられます。
つまり、腰の反りを強くすることで、上半身のバランスを取ろうと背中を丸める――これが「反り腰×猫背」の典型的なパターンです。
筋肉バランスの崩れが姿勢を固定する
骨盤まわりでは腸腰筋・大腿直筋が過緊張し、お腹まわりやハムストリングスが弱くなりやすくなります。
一方、背中側では胸の筋肉が硬くなり、背中の筋肉が引き伸ばされた状態に。
この前後のアンバランスが姿勢を固定し、「頑張っても姿勢が戻らない」状態を生み出します。
反り腰と猫背を整えるための考え方
① 「正しい姿勢」を目指す前に、まず“力を抜く”
反り腰・猫背のどちらも、姿勢を保とうとして無意識の力みが入っています。
まずは呼吸とともに腹部や背中の緊張を緩めることがスタートです。
浅い呼吸のままだと背中と腰の筋肉が固まりやすいため、腹式呼吸を意識してみましょう。
② 骨盤の動きを取り戻す
骨盤が前傾・後傾どちらかに固定されると、背骨全体の動きが制限されます。
仰向けで膝を立て、骨盤を「前に傾ける→後ろに傾ける」をゆっくり繰り返すだけでも、腰椎から胸椎までの連動が整いやすくなります。
③ 胸まわりの柔軟性を回復させる
デスクワークやスマートフォンの使用により、胸の筋肉(大胸筋・小胸筋)は硬くなりがちです。
壁や柱に腕を当てて胸を開くストレッチを行うことで、肩甲骨の可動域が広がり、背筋を自然に伸ばしやすくなります。
④ 体幹を「締める」より「支える」
姿勢を整える上で大切なのは、腹筋を力強く締めることではなく、インナーマッスルを使って支える感覚です。
おへそを軽く背骨に近づけるように息を吐くことで、深層筋(腹横筋)が働き、腰への負担を減らします。
ウェルクラフトが提案する“整える習慣”
日常で意識したい3つのポイント
- 1. 呼吸:浅く速い呼吸を避け、ゆっくりと腹式呼吸を行う
- 2. 立ち姿勢:お尻の下に重心を置き、膝と骨盤を一直線に
- 3. 座り姿勢:骨盤を立て、坐骨で座る意識を持つ
ウェルクラフトでは、姿勢の歪みを「筋肉・関節・神経・呼吸」の4つの側面から総合的に整えます。
施術で筋緊張を緩め、エクササイズで再現力を育て、栄養と教育で持続的な変化をサポート。
“整う姿勢”を自分で再現できるようになることを目指しています。
まとめ|姿勢を「直す」から「育てる」へ
反り腰と猫背は対立するものではなく、身体のバランスを保つために起こる一連の現象です。
大切なのは、姿勢を「直そう」とすることではなく、身体が自然に整う状態を育てること。
呼吸・骨盤・胸の動きを整え、日常の中で少しずつ「力を抜いて支える感覚」を身につけていきましょう。
ウェルクラフトは「整える力を育てる」ことを理念に、身体の理解と実践を通して“姿勢をデザインする”サポートを行っています。